初めての大学入学共通テストへの対処は?
国公立大学志願者の平均点は高くなる
国公立大学の志願者は減ると思います。2020年度は47万人から44万人へと3万人減りましたが、2021年度では40万人程度になるのではないでしょうか。これは、受験生の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)への拒否感が要因で、特に学力が中位以下の人は受験を見合わせるでしょう。第1回目となる共通テストの平均点は、厳しい結果になるとみられていますが、それでも国公立大学を第一志望にすえて合格を目指してきた人たちの平均点は、むしろ高くなると思います。

私立大学では上位校で共通テスト利用が増える
共通テストを避ける受験生がいる中、「MARCH」クラス以上の私立大学では共通テスト利用が増えています。早稲田大学は学部によって共通テストの利用はまちまちですが、上智大学はTEAP利用型を除けば共通テストが利用されるようになりました。学習院大学は新たに共通テスト利用型入試を始めますし、立教大学も英語は多くの学部で共通テストが必須となり、青山学院大学も学部個別型入試では、経済学部以外は共通テストが必須です
中堅クラス以下の私立大学は、推薦入試の出願要件を緩和
2021年度は一般選抜を敬遠する人が増えると先にお話しましたが、それは学校推薦型選抜・総合型選抜のハードルが低くなることとも関係があると思います。コロナ禍の影響で出願要件を緩くする大学が増え、特に中堅クラスとそれに続く私立大学で顕著になっています。従来、高校3年生の1学期までの成績で調査書を書くのですが、2021年度は2年生までの成績で良いなどとしている大学もあります。またスポーツ推薦では、県大会レベルの順位も問わずに書類を提出できる大学もあるようです。
共通テストでは、英語の出題形式に慣れることがポイント
駿台では7月の第2日曜日に共通テスト対策の模擬試験が実施され、私は御茶ノ水地区で受けた人に試験後の感想を聞いてみました。東京大学、京都大学志望者からMARCHクラスを狙っている人まで幅広く聞いたのですが、ほぼ全員が英語に苦戦したと話していました。「(センター試験より)難しくなった」「時間が足りなかった」などと言っており、特にリスニングに苦労したようで、今後はどれだけ新しい出題形式に慣れるかがポイントとなるでしょう。数学については、準備が進んでいない文科系の人は「ぼろぼろ」だったようですが、同じ文科系でも数学が得意な人や理科系の人にとっては、センター試験よりも明らかに易しく感じたそうです。また、国語、理科、地歴・公民は、センター試験の頃と難易度はほとんど変わらないと受け止めたようです。
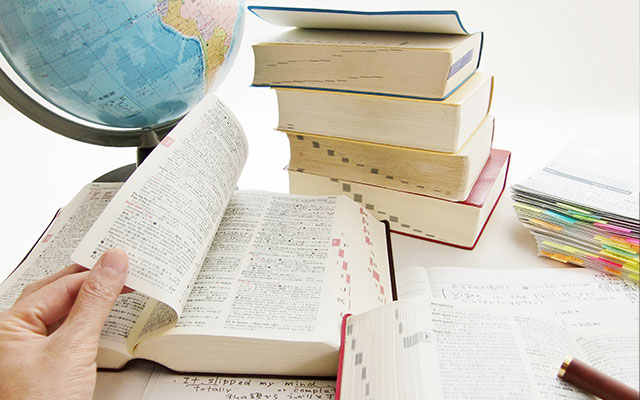
過去問がなく不安だろうが、共通テストは受けてほしい
共通テストを敬遠する理由の1つに、過去問がないことがあげられます。センター試験は過去20年間以上ほとんど傾向が変わらなかったので、過去問を解くことで傾向がつかめました。しかし、今回はまったくゼロからの対策になります。そのためボリュームゾーンである中堅クラスの大学を目指す受験生は、コロナ禍もあり共通テスト対策の模擬試験を受けることができていません。(一般の模試も受けることができない状態です)
確かに不安になる気持ちはわかります。でも私はあえて、「共通テストは受けたほうがいい」と言いたい。2021年度入試はコロナの影響でどうなるか、まだ分からないからです。
共通テストを受けた方がよい理由とは
共通テストは当初予定していた2021年1月16日・17日のほか、第2日程として1月30日・31日も設定されました。これは、コロナの影響による学業の遅れに配慮した措置で、出願時から第2日程を選択することができます。第2日程は、コロナへの罹患などを理由に第1日程で受験できなかった志願者の追試験としても実施します。また追試験では従来2会場としていた試験場が全都道府県へ拡大されます。しかも、第2日程を選択した志願者が病気などを理由に受験できなかった場合に備えて、2月13日・14日に特例追試験も実施します。
2020年度入試でもコロナの影響でこんなことがありました。北海道大学では後期試験が実施できず、大学はセンター試験の成績だけて後期合格者を出したのです。コロナは今後、まだどうなるかわかりませんし、入試日程にどんな影響があるのかも不透明です。2021年度入試でも、共通テストを受けて成績(得点)を持っていることは、有利に働く可能性があります。だから受けることをお勧めしたいのです。

自分に必要な教科だけでもトライして
共通テストは、私立大学文科系の人なら英語、国語と地理・歴史だけでもいい。少なくとも自分に必要な教科は受けておきましょう。ただ、共通テスト向けの練習はやらなきゃいけない。例年なら公開模擬試験が対策になりますが、模擬試験会場の収容能力がコロナの影響で例年の半分以下になっているため、オンラインの共通テスト対策の模擬試験を受けるなどで、試験に慣れてください。模擬試験を受けられなかった人は、予備校や受験関係の出版社などが販売している問題と解答を入手してください。入手したら、決められた試験時間を守って解いて自己採点する。そうやって共通テストの出題形式や問題に慣れていくことが大切です
大学の最新情報には高感度でキャッチアップ
コロナ禍にあって自分の目で志望大学の雰囲気を確かめることが難しい2020年は、以前にも増して大学が発信する情報のキャッチアップが重要です。また、新設学部・学科の情報にも、ぜひアンテナを広げてもらいたい。新設学部・学科の情報はコロナの影響であまり周知されていないため、受験の“穴場”になる可能性があるからです。例えば群馬大学に情報学部ができます。データサイエンス系なので本来なら人気が出そうですが、あまり知られていません。また、岡山大学が工学部と環境理工学部を改組して新たなデータサイエンス系の専攻を含む工学部を新設、名古屋大学と岐阜大学が連携して岐阜大学に社会システム経営学環を新設します。いずれも知っている人は多くはないはずです。私立大学でも國學院大学が観光学部を新設します。現在、観光業は厳しい状況に置かれていますが、卒業する4年後のことを考えれば、楽しみの方が大きいと思います。

勉強に打ち込める環境を生かして、頑張ってほしい
最後になりますが、受験生の皆さんに言いたいのは、一つは置かれた状況は全員一緒だということです。確かにオンライン授業ができたりできなかったりの違いはあるでしょうが、大した差ではありません。もう1つは、秋以降も受験勉強に打ち込める環境にあるということです。秋以降の学校行事もほとんどないでしょうし、冬休みも短縮されるでしょう。もう勉強するしかありませんね。高校の先生方はきっと皆さんの勉強のペースメーカーになってくれるはず。先生から与えられた課題は後回しにせず、毎日着実にこなしてください。そうすれば必ず、大学という目的地にたどり着きます。コロナに負けず、頑張ってください。
<取材日:2020年7月30日>