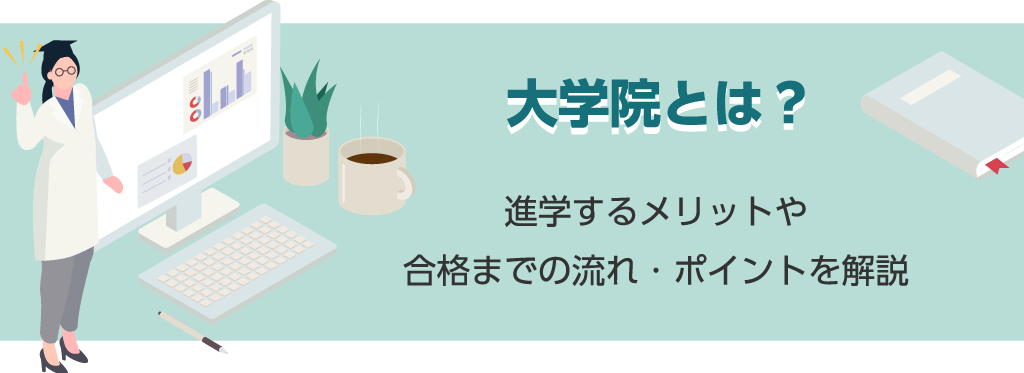
大学卒業後の進路には就職という選択肢がありますが、一方で大学院に進学する人も一定数います。大学院という場所で何をするのか、漠然と「研究をするところ」というイメージはあっても詳しくわからない高校生も多いのではないでしょうか。この記事では、大学院の定義、進学で得られるメリットとデメリット、大学と大学院の卒業後の進路の違いなどについて解説します。高校生・大学受験生には少し気が早いかもしれませんが、将来のキャリアへの参考にしてください。
大学院とは?|大学院の定義・2つの課程・入学資格
はじめに大学院の概要について、以下の項目に分けて解説します。
- ・大学院とは何か(何をするところか)
- ・修士課程と博士課程の違い
- ・大学院入試の種類
- ・大学院に進学するために必要な資格
- ・大学院受験と進学にかかる費用(修士課程)
大学院とは何をするところ?その定義
「大学院」とは、大学の各学部の上に置かれる教育機関を指します。そこでは大学で学び研究した課題について、さらに深く専門的に研究を行います。進学するタイミングは大学卒業後が一般的ですが、社会人になってから進学することも可能です。
教育と研究を行う研究系大学院(後述)では、大学での研究をさらに発展させるなど、より高度な研究を行って専門性を身につけられます。また専門職大学院(後述)では社会に貢献できるプロフェッショナルの育成を目指しています。どちらの大学院も、カリキュラムに沿った受け身の学習姿勢ではなく、自ら課題を発見し仮説を立て探究する積極的な姿勢が求められます。
(参考)中央教育審議会大学分科会:「大学院教育改革の推進について 〜未来を牽引する「知のプロフェッショナル」の育成〜(審議まとめ案)」
修士課程と博士課程の違い|通う年数など
大学院には「修士課程」と「博士課程」の2段階があり、前者を「博士課程(前期)」、後者を「博士課程(後期)」とも呼びます。大学・機関によっては「博士前期課程」「博士後期課程」との呼び方もあります。
| 課程 |
年数 |
取得要件 |
その他 |
| 修士課程 |
標準修業年限
2年 |
・2年以上の在学
・30単位以上の修得
・必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の合格 |
|
| 博士課程 |
標準修業年限
5年
・前期2年、後期3年の課程に区分する博士課程
・区分を設けない博士課程 |
・5年以上の在学
・30単位以上の修得
・必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験の合格 |
<論文博士>
大学院に在籍しなくても、博士論文の審査に合格し、かつ博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された場合。
<博士前期課程を修士課程と見なすこと>
大学院設置基準第4条第4項において、区分制博士課程の前期を修士として見なす規定はある一方、一貫制の2年間に関しては、特段の規定はない。(=あくまで博士課程の2年。一貫制博士課程が圧倒的に少ない一因か。) |
(出典)文部科学省:「修士課程・博士課程の関係について」,p2
修士課程とは
修士課程とは、研究者としての基礎を学ぶ課程といえます。既定の要件を満たすと「修士号(マスター)」という学位を取得できます。
修士課程の修了までに必要な年数は、原則として2年間です。ただし必ず2年在籍しなければならないわけではなく、優れた業績を上げた学生の場合などに、1年以上2年未満の在学期間でも修了できることもあります(大学院により異なる)。
修士課程修了に必要な要件は通常以下の3つです。
- ・2年以上の在籍(例外あり)
- ・30単位以上の修得
- ・修士論文の提出または特定課題の研究成果および審査・試験への合格
なお専門職大学院(後述)は修士課程のみとなります。
博士課程とは
博士課程とは、修士を取得した者が研究者を目指す課程です。修了要件を満たすと「博士号(ドクター)」という学位を取得できます。
博士課程の修了までに必要な年数は、原則として3年間です。修士課程と合わせると、原則として5年かかることになります。
博士課程の修了に必要な要件は通常以下の3つです。
- ・5年以上の在籍(修士課程2年を含む)
- ・30単位以上の修得(修士課程2年間での修得単位を含む)
- ・博士論文の提出および審査・試験への合格
以上は「大学院設置基準」による最低基準であり、あくまで「原則」のため、各大学院が定める修了要件とは異なります。それぞれの大学院の修了要件を確認してください。
なお、医・歯・薬学系の大学院は上記の要件規程とは異なります。医学部・歯学部は修士課程がなく、6年間の学部在籍後、博士課程に進みます。通常在籍年数は4年間です。薬学部は6年制の場合は医学部・歯学部と同じく博士課程へ進み4年在籍、4年制の場合は通常の研究系大学院と同じ修士課程2年、博士課程3年となります。
大学院入試の種類
大学院入試には「一般入試」と「社会人入試」があります。
一般入試(学部生入試)
大学学部生向けの入学試験です。大学により厳密な日程は異なりますが、おおむね夏から秋頃にかけて行われます。同じ大学の大学院に行く場合は内部進学として、一般の大学院入試と別に試験が設定されているところもあります。
社会人入試
大学卒業後に就職している(または大学卒の資格がなくても社会経験や専門的な経験を積んでいる)社会人向けの入学試験です。入学試験は学部生よりも遅い時期に行われる傾向があります(大学により異なる)。
大学院に進学するために必要な資格
大学院に入学するには通常、大卒資格である「学士号」の学位取得が条件であることが一般的です。ただし、学位号の取得は必須条件ではありません。大学院が個別に審査し「大学卒業と同程度と認める」あるいは「専門職に従事した経験が既定を満たす」と判断した場合などは、受験が認められる場合もあります。
大学院の2つの種類
大学院は大きく2つの種類に分けられます。ここでは「学術の教育・研究を主とする研究系大学院」と「高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院」について解説します。
研究系大学院とは
研究系大学院とは、各分野の研究者育成を目的とし、日本にある大学院のうち多くは研究系大学院が占めています。通常、大学3年生や4年生が「大学院に進学する」と言う場合はこちらを指すことが多いです。
専門分野の研究を行い、研究成果を論文にまとめます(修士論文・博士論文)。これを学位論文といいます。学位論文は各大学の指導教員や教授などから構成される審査委員によって、基準を満たしているか審査されます(公開の口頭試問など。各大学院・研究科によって異なる)。
研究系大学院は、さらに以下の3つに分類されます。
- (1) 学部を持つ大学の大学院:大学学部の上位機関として研究科をもつ大学院
- (2) 大学院大学:大学院のみの機関。大学の学部を持たないため、学生数が少ない
- (3) 独立研究科:大学院のみの機関。大学の学部を持たない。複数の専門分野を組み合わせ研究する。さまざまな学部の卒業生が入学する。
専門職大学院
裁判官、教員、その他社会のさまざまな方面で活躍する「人材の育成」を目的として設置された大学院は、専門職大学院と呼ばれます。具体的には、司法試験に合格し裁判官や検事、弁護士を目指す「法科大学院」、経営学の修士号であるMBA(Master of Business Administration:経営学修士)取得を目指す「経営大学院」などがこれに当たります。
研究系大学院が専門分野の研究を行うことを目的としているのに対し、専門職大学院は人材養成機関である点が大きく異なります。また専門職大学院では基本的に、論文提出の必要がありません。
大学院受験と進学にかかる費用の一例(修士課程)
大学院を受験し、進学した場合にかかる費用について紹介します。
(1)大学院の受験費用(検定料)
一般的に30,000円〜35,000円程度となっています。例えば国立の東京工業大学大学院では30,000円、私立の東京女子大学大学院では35,000円です。
(2)入学金
国公立大学は282,000円でほぼ統一されています(同大学卒業生への特待、公立大学の住民割引制度など、大学により減免制度もあり)。私立大学の金額は大学により異なります。
(3)授業料
国公立大学はおおむね年間535,800円ですが、例えば東京工業大学は635,400円となっており、大学ごとに異なるため確認が必要です。私立大学は年間100万円〜200万円と差があります。また同じ大学院でも研究科によって異なります。詳細は入学を志望する大学院の最新の案内を確認してください。
※各金額は2024年2月現在の情報
大学院に進学するメリットとデメリット
大学院に進学するとさまざまなメリットが得られますが、一方でデメリットもあります。進学を考慮する際は以下を参考に検討してください。
大学院に進学するメリット
大学院に進学することで以下のようなメリットがあります。
- ・自分のやりたい研究を充実した専門施設で集中してできる
- ・就職先の選択肢が広がる。特に理系分野は積極的に大学院卒を求める企業も多い
- ・就職後の給与(初任給)が大卒より高くなる
- ・大学院に進学することで、大学まででは得られない人脈が広がる
大学院に進学するデメリット
メリットの一方、以下のようなデメリットもあります。
- ・社会に出るタイミングが同学年の友人たちより遅れる
- ・研究で非常に忙しく、研究以外のことをする余裕がなくなる
- ・金銭的に負担がかかる(学生期間が延長となるため)
- ・必ずしも社会に出てから役立つスキルが身につくわけではない(研究系大学院の場合)
メリットとデメリットは表裏一体のため、自分にとってどの面を優先すべきか、どの面は許容できるかなど検討したうえで大学院への進学を決めるとよいでしょう。
大学院進学までのスケジュール
進学を決める時期から実際の試験の時期と合格まで、大学院受験の一般的なスケジュールは以下のとおりです。受験や出願に際しては、志望する大学院や各研究科の最新の募集要項などを確認してください。
なお、以下は研究系大学院のスケジュールになります。専門職大学院は研究計画書(自分の研究テーマ・目的をまとめた書類)の作成は不要なところがほとんどです。詳細は各大学院に問い合わせることをおすすめします。
(1) 3年次の冬まで|受験の意思決定・何を研究するか決める
遅くとも大学3年次の冬までに自分が大学院に行きたいのか、研究したいテーマがあるかを確認します。
大学にもよりますが、3年次までにある程度自分の学びたいことを決めてゼミに入っている学生の場合は、比較的「これを研究したい」という考えがまとまっているかもしれません。もし研究テーマが漠然とでも決まっていて、それが現在のゼミと関連性があるならば、ゼミの教授に相談してみてください。
ゼミに入っていない場合、研究計画書の作成を一人で行わねばならず、試験合格が困難になるおそれがあります。大学院に行きたいと突然思い立った場合でも、まずは大学や興味ある授業の教授などに相談することをおすすめします。
(2) 3年次修了まで|どの大学院の研究室を志望するか決める
同じ大学の院に進むのか、それとも別の大学院にするのか、情報を集め、自分のテーマが最も研究しやすいところを選びます。どの大学院というよりは、「どこの研究室ならば、どの教授ならば良いか」をしっかりと調べて探します。ゼミに入っているならば、指導してくれている教授に相談してみましょう。
このとき、志望する大学院を、その大学の偏差値で決める人がいますが、大学院入試に偏差値は無いと心得ましょう。最も重要なのは研究したいことを明確にすること、それに対する熱意と詳細な研究計画書を作成できるかどうかです。
(3) 4年次春|受験する時期・方式を決める
大学院入試は秋季(8〜11月頃)、春季(1〜3月頃)の2回、あるいはいずれか1回で行われるのが一般的です。どちらで受験するか決めましょう。
受験方式には、一般入試のほか、その大学院の大学学部生が進学する際に受けられる特別選考入試などもあります。
(4) 4年次春|説明会へ参加し、情報を取得する
大学院が開催する説明会があれば積極的に参加しましょう。また実際に受験して合格している先輩などがいれば、どのような対策を行ったか、いつ頃から何をしたのか話を聞いておきましょう。その他にも、ゼミの教授に相談するなど、できるだけ情報を集めることが大切です。
(5)大学院入試までに|研究計画書を作成し、その他の出願書類も揃える
研究計画書とは、大学院に入って自分が研究したいテーマについてまとめたものです。ゼミの教授などに相談すると指導を行ってくれる場合もあります。研究計画書の完成度が低く、大学院進学に適さないと判断されると、不合格になるおそれがあります。また手元にコピーを残し、口述試験に備えましょう。
そのほか、事務書類(成績証明書、志望理由書、卒業見込み証明書など)が必要です。詳しくは募集要項を確認しましょう。
(6)出願・受験
一般的に、大学院入試では筆答(筆記)試験と口述(面接)試験が課せられます。筆答試験は、専門科目と外国語科目(英語など)が多い傾向があります。過去問を調べ、対策しましょう。
口述試験では、特に研究計画書の内容について問われます。中には「そのテーマなら、うちじゃなくてよその研究室でもいいのでは?」などと反論されるケースもあるようです。あらかじめ、自分の研究テーマがどの分野なのか、その研究室・教授のどんな研究に惹かれ、自分もそこで研究してみたいと思ったのか、明確に伝えられるよう準備してください。志望理由書も含め、言っていることに齟齬が起きないよう、提出した研究計画書のコピーをよく見ておきましょう。
以上は一般的な流れですが、受験時期や受験方式、就職活動と並行して行うかどうかによって、着手する時期は異なります。なるべく早くスタートを切り、余裕のある受験スケジュールを立てましょう。なお、大学院受験のための予備校もありますので、利用する方法もあります。
大学院進学に関するQ&A
ここでは、大学院進学に関してよくある質問事項について回答していきます。
短大や専門学校からも大学院に入学できますか?
大学院に入学するための資格として、原則として四年制大学卒業による学士号取得が必要となります。よって、例えば短大卒の人が大学院に行くためには、基本的には大学編入試験を受験して四年制大学に入学しなければならないことになります。
文系・理系のどちらが大学院に進学しやすいですか?
2023年度(令和5年度)の文部科学省「学校基本調査」(以下、表参照)によると、文系分野よりも理系分野の方が合格率が高い傾向があります。
日本における大学院進学率の傾向には、文系と理系で数字上に違いが見られます。以下は政府による統計資料です。大学学部から大学院への進学率について、以下が読み取れます。
- ・工学は学部進学率が圧倒的に高い
- ・工学は志願者数も入学者数も他系統より突出して多く、合格率も高い
- ・合格率は文系(人文科学・社会科学)に比べると、理系(理・工・農)が高い
文系の合格率が低いことや文系・理系によっての社会人入学枠の違いなどについては、他にも考慮すべき情報があり、必ずしも「理系のほうが有利である」と言いきれるわけではありません。あくまでも傾向ですが、「理系のほうが、大学院への門戸が開かれている可能性がある」と考えられます。
将来的に大学院進学も視野に入れている高校生の方は、自分の志望大学・学部からの大学院進学ルートや合格率(難易度)についても合わせて調べておくとよいでしょう。
【表】大学院各分野進学者総数に対する入学者の割合と合格率
| 区分 |
大学院志願者数 |
大学院への入学者数 |
合格率(入学者/志願者) |
学部から大学院に進学した人の割合 |
| 人文科学
| 9,942 |
4,161 |
41.85% |
5.41% |
| 社会科学
| 17,779 |
6,376 |
35.86% |
8.30% |
| 理学
| 8,706 |
6,139 |
70.51% |
7.99% |
| 工学 |
42,954 |
33,294 |
77.51% |
43.33% |
| 農学 |
5,226 |
4,242 |
81.17% |
5.52% |
| 保健 |
7,646 |
5,550 |
72.59% |
7.22% |
| 商船 |
39 |
23 |
58.97% |
0.03% |
| 家政 |
538 |
415 |
77.14% |
0.54% |
| 教育 |
3,448 |
1,807 |
52.41% |
2.35% |
| 芸術 |
8,568 |
2,473 |
28.86% |
3.22% |
| その他 |
20,398 |
12,364 |
60.61% |
16.09% |
| 計 |
125,244 |
76,844 |
61.36% |
100.00% |
(出典)e-Stat学校基本調査 令和5年度>高等教育機関>学校調査>学校調査票(大学・大学院)>18「専攻分野別 大学院入学状況 2023年」資料より算定
※入学者数には5月1日現在在籍しない者は含まない。
※「修士課程」には,修士課程及び博士前期課程(医歯学,薬学(修業年限4年),獣医学関係以外の一貫制課程の1・2年次の課程を含む。)の入学志願者,入学者が含まれる。
大学院入試の難易度はどうやって調べればいいですか?
大学院入試には大学入試のような「偏差値」がありません。難易度については各大学院の合格率で判断するほか、志望する大学院に進学した先輩に具体的な話を聞いてみるなどして、情報を集めましょう。
大学院への受験と合格をサポートする「大学院予備校」もあります。合格率を高めたい人や、試験勉強を無駄なく行い効率よく合格を勝ち取りたい人は利用を検討してみてください。
大学院入試では、具体的にどのような試験をするのですか?どんな準備をすればよいでしょうか?
大学院の入試内容は研究科によって異なります。一般的には、事前に出された課題についてのレポートや小論文、試験官による口頭試問、英語などがあります。以下は2023年に大学院受験した実際の学生の例です。
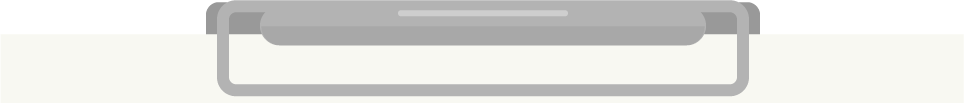
【私立4年制大学・心理学系】
(1)いつから大学院受験の勉強を始めたか
受験する年(3年次)の1月から(試験は4年次の7月)
(2)試験内容について
筆記試験:心理学についての知識の説明を記述する。
面接:出願時に提出した研究計画書をもとに、どのような研究をしたいか、入学・卒業して何をしたいかを問われた。
(3)どのような勉強をしたか
心理学における知識的な部分(脳機能、歴史、各心理学分野)と、研究法(研究に使う分析手法)、倫理的なものについての勉強を行った。
(4)なぜ大学院に行こうと思ったか
とにかく、心理学に興味があった。大学院でもっと深く勉強してみたいと思った。それに加え、公認心理士の資格に大学院卒が必要だったため。公認心理士になるかどうかはまだ決めていないが、将来の職業の選択肢として考えている。
一般企業への就職に有利かどうか、などは特に考えなかった。
(5)就職活動は行ったか
大学院進学のみ考えて準備したので、就職活動はしていない。
大学院や文系・理系によっても試験内容はさまざまです。また社会人入試や専門職大学院でも異なります。志望する大学院がある場合は、資料を取り寄せるなどして検討をすすめましょう。
なおこの学生のように、試験準備は、最低でも試験の半年前には意思決定して始めることが多いようです。大学3年生の冬は就職活動が本格化する時期のため、就職活動と並行して大学院入試の準備をする人は綿密かつ早めのスケジュールを立てる必要があります。
就職活動と並行して大学院の入試準備を行う場合の注意点はありますか?
大学生の間に一度就職活動を行っておくことは、大学院に進学した後にも役立ちます。修士課程を修了し就職する際にも、同じ就職活動を行うため一種の予行演習ととらえることもできるからです。そのため、大学院入試準備と就職活動を並行して行う場合は、「学部生のうちに社会や企業への見識を広める活動をしている」「2年後、または5年後の就職活動の練習だ」と前向きに受け止めましょう。
ただし、大学院試験のための準備期間は重要です。就職活動は、大学4年生の6月頃までに決まる人が比較的多いため、例えば大学院入試の秋試験(9月頃)を受験するならば、就職活動を終えてから院試験の準備をして臨むということも理論上は可能です。とはいえ、大学院入試の直前まで就職活動を行っていると、大学院入試対策が十分にできなくなります。
さらに就職活動と大学院入試対策を並行して行うときは、スケジュール管理とともに体調管理も重要になります。例年、6月前後には教員免許取得に必須の中高での教育実習が行われるほか、卒業論文の準備も始まっています。該当する人の場合、それらを全て並行して進めることはかなり難しいと認識して臨んでください。
何より、「就職に失敗したら大学院に行けばいい」という消極的な考えでは、どちらも失敗することになりかねません。就職するのか大学院に進学するのかは、できれば3年生の秋頃までには決めておいたほうがよいでしょう。就職するにしても大学院に進学するにしても、自分が何をしたいのか、将来のビジョンを明確にしたうえで行動することが大切です。
大学院卒でなければ受験できない国家資格にはどんなものがありますか?
大学院卒が受験条件となっている国家資格には、例えば以下のようなものがあります。これらの資格を目指す人は早めに準備を進めることが肝心です。
大学院を卒業し修士号を取得することで目指しやすくなる職種はありますか?
一般論になりますが、大学教員や民間企業の研究員などは大学院修了が必須条件ではないものの、就業者に大学院修了者が多くを占めるといわれます。また、理系企業では大学院卒生を多く採用する傾向があるようです。
その他、近年ではシステムエンジニアなどのIT職、IT系・金融系・経営戦略系コンサルタント職で大学院修了者を求める企業も増えています。
まとめ
この記事では大学院とは何か、大学院の種類や入試について、大学院に進学するメリットとデメリット、大学院入試までの流れ、その他大学院への進学を考える際に気をつけたい点について解説しました。
大学院に進学すると、研究分野における高度な専門性を身につけられ、その知識などをもとに企業での就職の間口が広がるなどのメリットがあります。しかし何よりも、メリットやデメリットで計るのではなく、自分が興味のある分野について深く極めたいという学究的な欲求をもって進学を目指すことが大切です。また将来つきたい職業が学士号以上の学位を必須としているならば、大学院進学によって夢をかなえられるでしょう。
記事提供
塾探しの窓口は小・中・高校生向けの塾検索サイト。大手学習塾から地域密着型の個人塾まで全国300以上の学習塾を掲載中です。お子様の成績や受験にお悩みの保護者様に向けて、塾選びの基本知識や家庭学習のコツ、高校受験・大学受験の対策ポイントなど、お役立ち情報を毎月発信しています。毎年のように変化する入試制度、合格を勝ち取るには最新情報や受験ノウハウを得るのは必須。情報源の一つとしてぜひお役立てください。